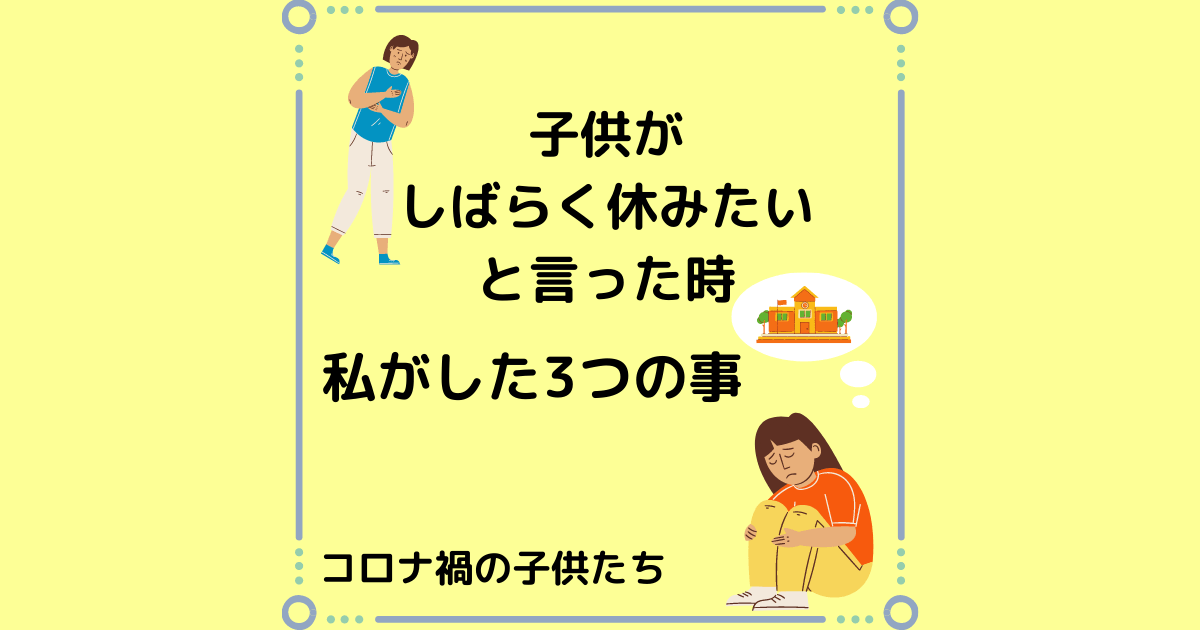コロナ疲れ、出ていませんか?
夏休みが終わるころ、現在小学3年生の娘が
「しばらくお休みしたい」
と言ってきました。
私はとても驚きました。
娘は9月が近づくにつれて、お友達に会いたいとか、学校楽しみとか言っていたからです。
同じように悩んでいる方、まだ子供が小さいけれど興味のある方に、こんな家庭もあるよ、こんな考え方もあるよと参考になることがあればと思い、記事にしました。
娘が休みたいと言った理由

突然の告白に驚きを隠せなかった!
でも、理由があるんだよね?
娘が「しばらくお休みしたい」理由は給食が怖いことが理由でした。
我が家は、コロナが流行り始めた2020年春頃からほとんど外食をしていません。
外食産業の方や生産者さんには申し訳ないのですが、娘はアトピーがあり目をこする癖があります。
私もアトピーの名残か顔を無意識に触る癖があります。
その理由から他の方よりウイルスの接触のリスクが多いと思い、なるべく避けるようにしていました。
また、2021年の夏、コロナ患者の急激な増加のニュースを垂れ流しにしてしまい、娘に恐怖を与えてしまったのかもしれません。

視覚優位ってわかってるのに・・・
そりゃあんなニュース見てたら怖くなるよね・・
真剣な顔をして言ってきた娘に対して、私も真剣に捉えなくてはいけないと思いました。
きっと、計り知れない勇気をだして言ってくれたんだと思う。
じゃあ、私がすること、してあげれれる事ってなんだろう?
ずぼら主婦もこの時ばかりはフル回転で頭を回して考えました。
私がしたこと3つ
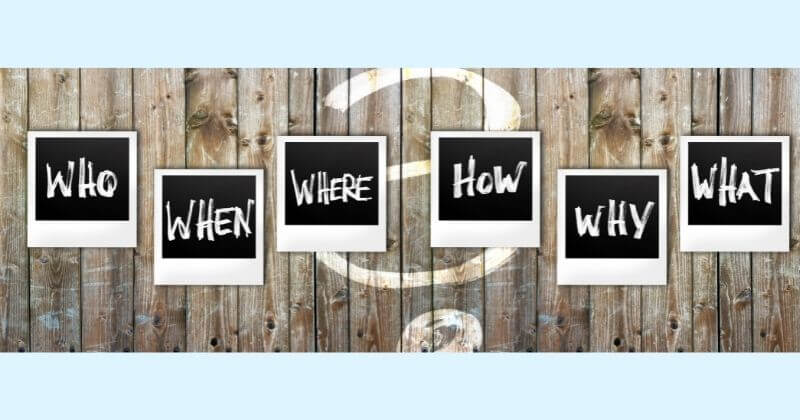
あと数日で学校が始まるというタイミングだったので、私の心はぐっちゃぐちゃでした。
(今まで普通に通えたのになんで?)
(このまま学校にすら行きたくないって言ったらどうしよう)
(このことがきっかけでいじめられたらどうしよう)
色んな考えがバーッと浮かんできました。
でも、この問題は私の問題じゃないんですよね。
だから解決できなくて余計に悩む。
このことで困っているのは娘なんです。
私が出来る事は、娘に寄り添って困りごとを減らせるようにする事だと思い直しました。
そして以下の事をやってみました。
否定しないで話を聞く
まず、娘がどうして「しばらくお休みしたい」「給食が怖い」と思ったのかを教えてもらいました。
その時私は聞くだけに集中します。
すぐに否定したり、私の意見を言わないよう努力しました。
いつもなら、口出ししてしまう私にとってはとても難しかったですが、この機会を逃してしまったら子供は今後困りごとを言えなくなってしまいます。
イメージとしては、事情聴取?

なんか、怖くない?
怖さは出さないで、子供が感じていることを言葉にしてもらいました。
感情を言葉にするという事は、大人でも難しいですよね。
子供が言葉に困っているときは、こういう感じかな?とヒントになるような声かけはOKです。
すると娘から、
- コロナの感染が子供も多くなってきて怖いということ
- マスクを外す活動が不安だということ
がわかりました。
とにかく話を聞いてあげる事が大切です。
子供にとっては勇気を出しての行動だったかもしれません。
否定や意見をせずじっくり聞いてあげることで気持ちが落ち着く事もよくあります。
出来る事、出来ないことを一緒に考える
娘の気持ちが聞けたので、これからどうしたらいいかを話し合いました。
娘からはマスクを外す活動が怖いという事がわかったので、学習などのマスクをつけて行う活動は出来るという事がわかりました。
つまり、今回は給食を学校で食べたくないという事でした。
具体的な行動としては、午前中の授業終了後早退する事が娘の希望です。

「しばらく休みたい」から具体的な行動がわかった!
でも実際どうしよう・・・
ここからは、その希望について実行できるかを家族で考えていきます。
家族で行動する以上、こちらが出来る事出来ないことを理由を添えて説明するのが大切だと考えます。
今回は、私の予定が特に無いので学校に迎えに行く事は可能だったので、9月いっぱい早退する事になりました。
ただし、ワクチン接種などの予定はずらせないので、私が体調不良になった日は迎えに行けないので娘も学校を休むという事を理解してもらいました。
話を聞いて、娘の希望する具体的な行動(出来る・出来ない)を一緒に考る事が大事。
子供の希望を100%叶える事が難しいことを理解してもらう。
叶えてあげたい気持ちがある事、その上でどうしても出来ない事がある事をゆっくりでいいので理解してもらう。
言っても無駄なんだ、結局わかってくれなかったという思いをさせないためにここは時間をかけました。
子供に行動する覚悟を決めてもらう
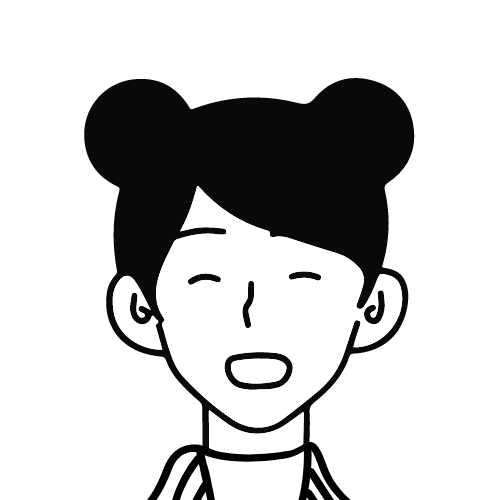
少し心が軽くなったよ♪
先生やお友達と会うのは楽しみなんだ!
上記の話し合いである程度方向性が見えてくると、娘の顔もホッとした顔になってきました。
これはうちの子だけかもしれませんが、ちょっと調子に乗るところがあるので、最後に少し厳しいようですが、行動する事に対しての覚悟をきちんと決めてもらいました。
- 自分で決めたことなので責任をもって行動する事(この期間中は外食もなし)
- 決めた期間は途中で変えられない事(欠食届を出しているため)
- 授業に出られない時間はどう行動するか自分で考える事(授業の時間は自宅学習する事に)
- 周りの人にも感謝を忘れない事(先生やクラスのお友達にも迷惑をかけるかもしれない)
色んな価値観があって、その中で自ら決断をしていく事は悪いことではなく素晴らしい事なんです。
でもいざ自分の子供が集団から外れて行動したいと言われたら、とても戸惑いました。
娘にも覚悟を決めてもらうといいつつ、覚悟を決めなくてはいけないのは親の方なのかもしれません。
一緒に覚悟を決める事が出来て、家族で心が一つになれたような気がしました。
実際にやってみて
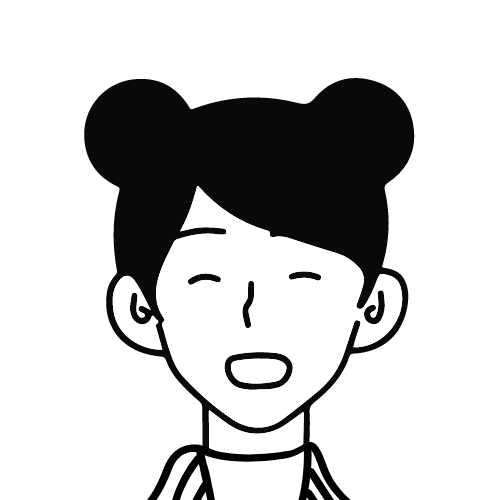
学校はやっぱり楽しいね♪
初めて迎えに行くときは、私も緊張しました。
ちょうど給食の準備で学校全体がバタバタしている時間だったので申し訳ない気持ちもありました。
初日こそ、「なんで帰るの?」と聞かれたりしましたが、数日たつと「迎えが来てるよ!」とクラスのお友達が娘に声をかけてくれたり、普通に「またねー」と別れる様子を見ることが出来て私も楽しかったです。
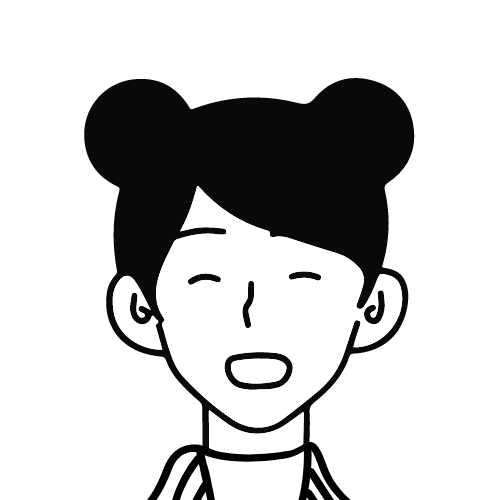
コロナが怖いから、給食食べないって自分で決めたんだ!
お友達に聞かれたら、そう答えたよ♪
みんなわかってくれたし、協力してくれて嬉しかったな。

でも、毎日の迎えは大変だった!!!
暑いし、日頃の運動不足が・・・
あと、お昼の用意もーー!!
休む授業は、オンライン授業はありませんでしたが、自宅での課題を先生も考えてくれて、とても有難かったです。
娘もお友達や先生に協力してもらって、早退する事が出来ているという事を感じて、最終日には先生に感謝のお手紙を渡していました。
そして、10月以降は、給食を食べるとのことで、現在は早退せず通っています。
コロナ禍の子供たち

娘をはじめ、コロナ禍の子供たちは色々な不安を抱えているんだなと最近よく感じます。
自分の娘以外にも周りの子も、怒りっぽかったり、癇癪を起したり、マスクに対して敏感だったり(マスク警察系)、疲れやすかったり・・・
それは、コロナ禍の雰囲気から来ているのではないかと私は考えます。
2021年10月現在、コロナ禍と言われてもう1年半が過ぎようとしています。
子供も大人も、ゴールの見えない世界で疲れ果ててます。
そんな中、自分が大丈夫じゃないときには、子供とはいえしっかり受け止める事は難しく感じました。
大人も大変な時は頼れるところに頼ろう
今回の件は、家族以外相談せず決めました。
各家庭でコロナに対する考え方が違うので、相談する事に抵抗がありました。
(否定されたらどうしよう・・・)
他にも育児の事に対して、同じ学校のママさんには相談しにくいけど、誰かに聞いて欲しいなという事もあると思います。
そんな時に、文部科学省のHPに家庭教育支援チームという活動があるのを見つけました。
家庭と地域や学校をつなぐ家庭教育支援チーム
家庭教育支援チームは、ご家庭での皆さんの頑張りを共に支え、地域とのつながりづくりや専門機関との橋渡しをお手伝いします!
文部科学省では、悩みや不安を抱え、孤立しがちな家庭や仕事で忙しい家庭など、待っていては支援が届きにくい家庭への支援の充実を図るため、平成20年からの2年間、子育てサポーターや教職員経験者、民生委員・児童委員、保健師、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーなど、地域の様々な人々や専門家による「家庭教育支援チーム」を組織し、学校等と連携して、親同士のつながりづくりや相談対応を行う取組を、全国各地で行いました。
こうした取組を進める地域を引き続き応援するため、現在は、家庭教育支援チーム活動支援制度を設け、効果的な事例や情報の提供などにより、子育て・家庭教育支援の取組が充実されるよう努めています。
文部科学省家庭教育支援HPより引用
こちらのHPでは、地域ごとに活動しているチームが紹介されているので、お住いの地域に支援チームがあるならお子さんと一緒でも、親だけでも、参加してみるのもいいと思います。
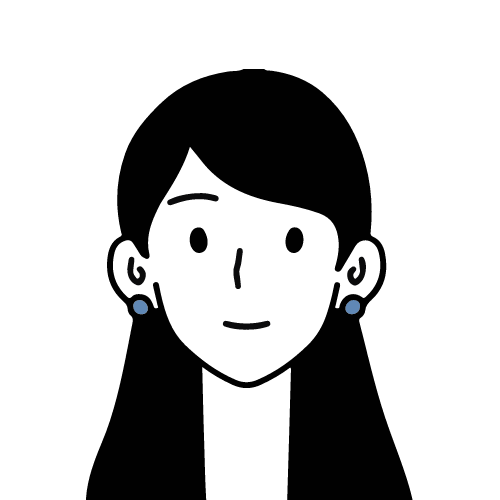
でも、参加するって勇気がいるなぁ・・・
もし、参加しなくても、こういう活動をしているチームが地域にあるという事を知っているだけで、何かあったときに心強いと思います。
最後に
我が家の9月の出来事をお話ししました。
今回はマスクを外すことが怖い→給食は食べないで帰りたいという問題でしたが、その他の学校や生活での困りごとにも当てはまるのではないかなと思い記事にしました。
学校に行きたくない、習い事に行きたくない、等どんな問題が娘の中にあっても今回のようなやり方で前に進むことが出来るなと感じました。
また、今回は私が家にいるから迎えに行く事が出来ましたが、仕事などで迎えに行けない場合などでも、出来る事、出来ない事をきちんと話うことで子供と折り合いをつける事が出来ます。
親も子供も、いろんな出来事があると思います。
問題が小さいうちに受け止めて、こちらの意見も受け止めてもらって、一緒に問題解決をしていけば、きっと乗り越えられると思っています。

長々と、最後までお読みいただきありがとうございました。
読んでくださった方の心が少しでも軽くなってもらえたら嬉しいです。
にほんブログ村